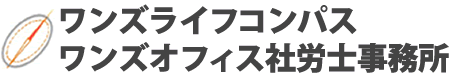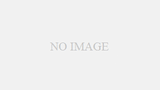― 働き方の自由・自己責任論を超えて ―
労働時間規制の「緩和」や「弾力化」に関する議論が始まっている。しかし、その多くはホワイトカラー層や専門職を念頭に置いた議論にとどまり、国民生活の基盤を支える「社会インフラ職種」――介護・看護・建設・インフラ設備保守・解体など――をどう守り、持続させるかという視点が欠けていると考える。
これらの職種は、時間とマンパワーが不可欠であり、AIや機械化では代替しづらい。にもかかわらず、賃金水準は低く、身体的・精神的負担が大きい。かつては日本人労働者が支えてきた分野だが、今や人材不足が慢性化し、国の「最低限の安全と健康」を支える力そのものが揺らぎつつある。
◆ 医師の時間外規制対策に学ぶ
例えば、勤務医師の働き方改革では、夜勤・宿直など過酷シフトに対する手当付与制度や、医療チーム全体で勤務時間を調整するチーム単位の労働時間管理が導入されている。
この仕組みは、「必要不可欠な職務を担う人々の健康と使命の両立」を目的とするものであり、同様の発想を社会インフラ職種にも拡張できないだろうか。
◆ 政策の方向性として
- 社会インフラ職種の再定義と基金創設
介護・看護・建設・インフラ保守を「社会インフラ職種」と位置づけ、賃金補助・教育訓練・安全対策を支援する国家基金を創設する。
→ 公共事業と同等に、国民生活維持の基盤として支える。 - 労働時間緩和ではなく、労働環境改善への投資
長時間労働を容認するのではなく、業務のチーム化・デジタル化・人員配置の最適化に公的支援を集中する。
→ 「長く働くしかない」構造を脱する。 - 国内人材の流入促進と再教育支援
現場労働を「やむを得ず」ではなく「選ばれるキャリア」とするために、資格取得・訓練・住居支援をセットで行う。
→ 地域定着と誇りのある職務化へ。 - 外国人労働者を補完的に、公平に受け入れる制度設計
短期的な穴埋めではなく、教育・安全・生活支援を含めた中長期の人材育成枠組みを念頭に置く。
◆ 結語
社会を支える仕事を放置することは、国家としての機能を衰えさせる。
単に「働き方の自由」や「自己責任」及び「民間企業の労務管理改善」で片付けるのではなく、社会インフラを維持するための労働政策として再構築することこそ、真の方向性である。
現場を支える人々の健康と誇りを守ることは、国の維持発展において重要であると考える。